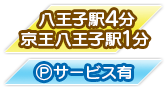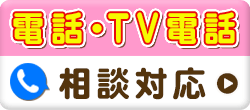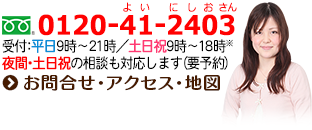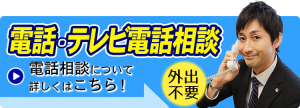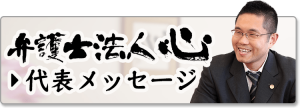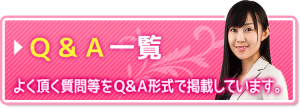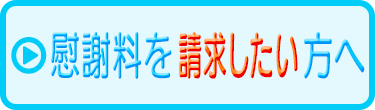不倫慰謝料に関する示談書作成についてのQ&A
Q示談書は作成した方がよいのですか?
A
結論から申し上げますと、不倫慰謝料についての話し合いがまとまったら、示談書は作成するべきです。
法律上は示談書を作成する義務はありませんが、示談書を作成するメリットは大きいといえます。
合意した内容を客観的に証明することができ、もし合意したことが守られない場合には訴訟提起の際の証拠として用いることもできます。
示談書を作成していないと、約束を反故にされても、そもそも約束した内容を第三者に対して証明することができません。
示談書に当事者が押印をする際には、後になって示談書を偽造されたという主張がなされることを抑止するため、実印を用いて印鑑証明書を添付することが多いです。
また、示談書を強制執行認諾文言付公正証書で作成しておくと、慰謝料が支払われない場合に、訴訟を提起しなくても強制執行をすることができます。
Q示談書には何を記載すればよいですか?
A
示談の中核となる慰謝料に関しては、その金額と、支払期限、支払い方法(手渡し、銀行振り込みなど)を明確に記載します。
守秘義務や、不倫をした配偶者と不倫相手との連絡を禁じる旨など、慰謝料の支払い以外についての取り決めがある場合も、具体的に記載します。
また、これらに違反した際の違約金の定めを記載することもあります。
示談後に不倫慰謝料に関する争いが蒸し返されることを防ぐため、清算条項を定めておくことも大切です。
Q示談書には記載するべきでないことはありますか?
A
当事者の行為を制約する範囲が広すぎる条項や、過剰な要求(勤務先を辞職することや、遠方に転居することなど)を反映した条項は、公序良俗に反して無効となることがあります。
Q示談が無効になることや取り消されることはありますか?
A
あまり多くはないと考えられますが、当事者本人またはその代理人以外が交渉や示談をしたとしても、そもそも示談は不成立となります。
当事者の親族などが間に入っていることもあり得ますので、話し合いや示談書の作成の際には、本人確認(代理人の場合には代理権を示す委任状等の確認)をすることも有効です。
また、示談の際に、詐欺・強迫・錯誤による意思表示があると、民法上は取り消すことができる状態になります。
例えば、相場を大きく外れた法外な慰謝料を提示し、示談に応じない場合には、不倫の事実を勤務先に伝えることを告知するといった脅迫がなされることは考えられます。
脅迫により、やむを得ず示談書に署名、押印をしたという場合、示談を取消し得るといえます。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒192-0046東京都八王子市
明神町4-7-3
やまとビル3F
0120-41-2403